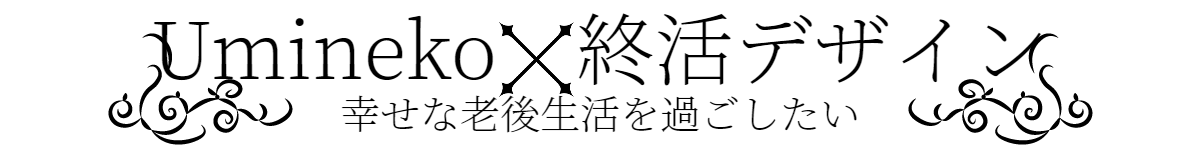相続で家族が揉めないための財産目録作成ガイド!
「うちは財産が多いわけではないから大丈夫」—そう思っている方ほど、注意が必要です。
家族間の相続トラブルは、資産の多寡ではなく、「情報の不足」と「不公平感」から生まれることがほとんどです。特に、故人の銀行口座の存在や借金の有無が不明な場合、残された家族は手続きで膨大な手間と精神的な負担を強いられます。
結論からお伝えします。 家族の金銭的なトラブルを未然に防ぎ、スムーズに相続手続きを進めるには、「財産目録」を作成しておくことが、親としてできる最高の準備です。
この記事では、財産目録を誰でも簡単に作成できる手順と、家族が揉めないための具体的な書き方のコツを、ひな形とともに解説します。
1. 財産目録とは?なぜ家族が揉めないために必要か
財産目録の定義と目的
財産目録とは、あなたの持つすべての財産(資産・負債)を一覧にしたリストのことです。
これは法的に作成が義務付けられている書類ではありませんが、終活において遺言書以上に重要だと言われることがあります。
【作成の最大のメリット】
- 「隠し財産」による不信感を防ぐ: 家族に存在を知られていない口座や資産があると、それが後から発覚した際に「他にも何か隠しているのでは?」と不信感が生まれ、トラブルの火種になります。
- 相続手続きの時間を大幅に短縮: 家族が故人の資産を探し回る手間がゼロになります。銀行名や口座番号が分かれば、すぐに手続きに入れます。
- 借金(負債)の有無を明確にする: 負債(ローンや借金)がある場合、家族が「相続放棄」すべきかを速やかに判断できます。
2種類の財産を漏れなくリストアップする
財産目録には、必ず「プラスの財産(資産)」と「マイナスの財産(負債)」の両方を記載します。
2. 誰でもできる!財産目録の具体的な作成手順
財産目録の作成は、以下の3ステップで進めればスムーズです。
Step1:資料を集め、すべての財産を洗い出す
まずは、あなたのすべての資産と負債の「証拠」となる資料をかき集めます。
- 預貯金: 過去1年分の通帳のコピー、残高証明書など。勿論通帳本体もOK。
- 不動産: 権利証(登記識別情報)、固定資産税の納税通知書など
- 保険: 生命保険・火災保険などの証券、年金のねんきん定期便
- 負債: ローンの残高証明書、借用書のコピー
特に使っていない休眠口座や、昔入ったまま忘れている生命保険などは、この機会に徹底的に洗い出しましょう。
Step2:目録のひな形に項目を記入する
集めた資料に基づき、財産目録を形式に沿って作成します。
手書きでもPC入力でも構いませんが、エクセルなどの表計算ソフトで作成すると、集計がしやすく、項目を追加・削除しやすいのでおすすめです。ですが、わざわざパソコンを買って、エクセルの書き方を覚えてなどをしていると時間もお金も無駄になります。その場合、チラシの裏でも無くさなければ構いません。
(※【財産目録のひな形イメージ】は記事の最後にまとめています。)
【作成時の必須ルール】
- 金額は「いつ時点」かを明記する:残高や評価額は変動するため、「令和〇年〇月〇日時点の残高」と必ず記入します。
- 評価額は正確に: 不動産や株式などは正確な評価額の記載が難しい場合があります。その場合は、「固定資産税評価額」や「概算の市場価格」を併記しておくと、家族が判断しやすくなります。
Step3:保管場所を家族に伝え、定期的に更新する
財産目録を作成しても、家族がその存在を知らなければ意味がありません。
- 保管場所: エンディングノートや重要書類と一緒に保管し、その場所を家族(特に相続人となる方)に伝えておきましょう。
- 更新頻度: 預貯金や株の残高は常に変動するため、最低でも年に1回は更新し、最新版を保管するようにしてください。新年あるいは年末の行事として家族で情報を交換し合うのも良いと思います。
3. 相続トラブルを防ぐ!財産目録の書き方のコツ
財産目録は「単なるリスト」ではなく、あなたの「意思」を伝えるコミュニケーションツールです。
コツ1:マイナスの財産を「最上段」に書く
借金やローンなどの負債(マイナスの財産)は、必ずプラスの財産よりも先に、目立つように記載しましょう。
なぜなら、もし資産よりも負債が上回る場合、家族は「相続放棄」という重要な決断を死後3ヶ月以内に行う必要があるからです。負債の存在をすぐに家族に伝えられるように配慮しましょう。
コツ2:デジタル資産の「アクセス情報」を必ず添える
最近、問題になりがちなのがデジタル遺産です。
- デジタル資産の例: ネット銀行、ネット証券、ポイント、仮想通貨、有料サービスのサブスクリプション(Netflix、動画配信など)。
これらは目録に金額を記載するだけでなく、「サービス名」「ログインID」「問い合わせ先」を必ず記録します。(※セキュリティの観点から、パスワード自体は別の安全な場所に保管し、その保管場所を目録に記載するのがおすすめです。)
コツ3:「付言(ふげん)」で想いを添える
財産目録に、法定相続分とは別に「この資産は〇〇に譲る」といったあなたの意向を書き添えることができます。(※法的な効力はありませんが、家族の納得感を生みます。)
- 記載例: 「この自宅は長男が住み続けることを希望します。その代わり、預金は均等に分けてください。」
あなたの意思を付言することで、遺された家族は「故人の希望だったから」と納得しやすくなり、争いを避けることができます。
しかし、一番良いのは遺言状を書くことです。下の項目でも述べてますが、遺言状は法的拘束力があるため強制力があり、そもそも争族が発生しずらくなります。ただ、揉める可能性は減りますが、「家族のことを信用していないのか」ととられる場合もありますので、ご家庭の事情に合わせて適宜判断してください。
4. 財産目録だけでは不十分?法的な効力を持たせるには
財産目録は非常に重要ですが、法的な効力はありません。これはあくまで家族への「情報提供」にすぎません。
あなたの意思を法的に確定させ、確実に相続させたい場合は、「遺言書」が必要です。
特に以下のケースに当てはまる方は、遺言書の作成を強くおすすめします。
- 特定の財産を特定の人に譲りたい(例:自宅は長男に)
- 法定相続人以外の人に財産を贈りたい(例:孫や内縁の妻)
- 家族構成が複雑である(再婚、前妻との間の子がいるなど)
▶︎ 遺言書の作成に不安がある方へ: 遺言書は法律に従って作成しないと無効になる可能性があります。公正証書遺言の作成や、自筆証書遺言の検認手続きなど、専門的な知識が必要です。
家族が揉めるリスクを最小限に抑えるためにも、弁護士や司法書士といった相続の専門家へ無料相談することを強くおすすめします。